
文が消失しました…ラプソ時代のシーアの世話役(?)はシグルドなんですという話

文が消失しました其の二
表側では没にしたネタです

目の前で、剣を突きたてようとして来た男の身体がくの字に曲がり飛んでいく。壁に激突してそのまま床にずるりと落ちて行く間に、ぶぅんと音を立てて紅が暗闇に舞った。ひとり、ふたり、周囲に集っていた男達を薙いで紅は目の前に制止した。草色のバンダナに纏め切れなかった黒髪が、風に揺れている。
「ごめん、遅くなった…平気か、シーア」
「…レイ」
居るはずの無い人物に、ただ視線を向けるだけだった。
「ポーラの所へ先に駆けつけてしまったんだ、向こうもまだ幾らか数がいる、だから僕が先に来た」
「ポーラは」
「大丈夫、無事だよ。流石風を得意とする人だ、落ちた時の怪我はひとつもなかったみたいだ」
強張った肩の力が抜け、徐に滴る赤の雫を片腕で拭う仕草にレイは顔を顰めた。明らかに彼女よりも、彼の傷の方が酷い、闘える身体ではないというのは判っていたが、全身につけられた急所を避けた刃傷はどう見ても嬲られているとしか言えない。
「レイ、…レイ・マクドール」
辺りに群がる男達から、地の底から響いたかのように低い音が漏れた。暫し思案の後に、
「…生と死」
じりと彼の気配に殺気が混じったのを、シーアは見逃さなかった。レイは構えていた身体を解き、姿勢を正す。それは武器を交えるときの姿ではなく、敵や仲間の前に姿を見せる時の一切の隙も見せない、英雄の姿だった。
だん、と棍を床に叩きつけて、男達を睨みつける。
「それが何か。よもや私からこれを奪おうとでもするのか。
だが残念な事だが、この紋章は災いを呼び寄せ、そして災いから私を護る。奪おうとした所でお前たちの命が失せるのが先だろう」
「…成程」
闇に、先ほどと同じ音が流れる。
「それも、似た呪いを持つものか…」
似た呪?
顔を顰めて、ふと気付きレイはささやかに視線を背後へと移した。壁に寄りかかっていた筈のシーアは身体を起こし、立ち上がれず膝をついたままだが、それでも剣を携えていた。その身体の傷を、見る。
全身にあると思っていた傷は、良く見れば、左の腕には殆どなかった。偶然ではなく意図的に、左の腕には刃を向けていなかったのだ。その訳は、今はもうよく判っていた。
「…だからポーラがあんなに必死だったのか」
勘が鈍ったなと思うと同時に、己はとても運が良いのだと実感する。この呪いの紋章を持って、思い通りに制御出来ないまま…それでも平穏な二年を過ごしたのは奇跡としかいえないのだと。
ぶぅん、と音を立てて棍を回す、片足を引き体勢を整えて、レイは表情を消した。
「すまないが、わたしのこれも、彼の罰も…渡すつもりは無い。
…来るなら力ずくで来い」
「レイッ」
なにを、と続けられる筈だっただろう言葉は、赤が舞うことで途切れた。投剣を弾き、向ってくる男の剣先を棍で流す。棍を突き出して男の喉元を突き、振り返り様に薙ぐ。ぎぅんと音を立てて短剣がシーアの足元に落ちた。
魔力が溢れるのを感じて、シーアを背に構えた。レイ、と叫びそうになる声が聞こえたが、その音は直ぐに魔を紡いだ。
「土の守護神」
金の光が溢れ出し、目の前まで迫っていた炎の塊を四散させる。
「シーア、無理をしないでいい」
「それは僕の台詞だ、僕を庇って尚一人では無理だ」
「その身体で戦うなんて、かえって気になってしまう」
「けれど…っ」
「シーア」
ぎぅんと音をたてて剣を弾く、飛んできた投剣を防ぎきれず肩に掠めて服の端が裂けた。尚降り注ぐ銀の煌めきに恐れもせず、高揚もせず。
静かだと、レイは思う。
「今貴方を護らないで、僕はいつ貴方に恩を返せばいい?」
前は親友を助ける為に己の危険を顧みず奔走した彼を感情のまま殴り飛ばした。今回は失った親友を呼び戻す為に命を削らせた。
自分が彼にしてしまった仕打ちを帳消しにするには、これ一度きりでは返しきれないだろう。
それに。
「ここで護れなかったら、あいつにまた殴られる」
苦笑が漏れた…状況は決して楽ではないのに、余裕を保てる自分が居た。侮辱ととったのか男達の気配がざわりと揺れる。更に笑って、姿勢を正そうとした時だった。
腕をとられて、身体が後退する。突然の事にレイは眼を見開いて、一瞬だけ腕を掴む掌を見る。包帯が解けて、渦の形をした痣が浮かび上がる左の甲。何を、と声に出そうとした時だった。
「…君は」
小さく、彼が囁いた。
「彼の本当の矢を、見た事があるだろうか」
「…え」
「ならば、じっとしていた方がいい」
巻き込まれたくなければ。
そう呟いたのと、訝しげに見ていた男たちが一斉に動き始めたのが同時。その中に、
だん。
と異質な音が響くと共に、男が一人胸を抱えて倒れた。
一瞬何が起こったのかレイも男達も判らなかった、その僅かな時間の合間にまた男が一人、胸に細い棒を突きたてられて崩れる。その時漸くそれが矢だという事にレイは気付いた。そういえば、とレイは思う。自分たちが立っている場所のすぐ後ろは、魔法でだろう、壁が崩れていた。その脇の窓は全て硝子が砕け、窓枠だけになっていた。
その微かな間を縫って、矢は淡々と容赦なく男達に降り注ぐ。気付いた時には一人を残して、全ての男達が床に横たわっていた。
最後に残ったたった一人は、肩に矢を受けながらも辛うじて急所を狙う矢をなぎ払い生き残っていた。だが既に仲間はいない、じりりと後退りをするのを見、逃しても良いのかと一瞬考えが過ぎる。
けれど今はシーアの身を護る事を優先させるべきだと、見逃そうとした、その刹那。ひゅんと音を立てて銀の輝きが暗闇に舞った。男は辛うじて気付き後ろに避けた、しかしその煌めきの方が、早かった。
深く深く、それは胸の中へと滑り込む。呆然とそれを見やった後、男の掌から剣が零れる。からりと乾いた音を立てて剣が落ち、男の身体が崩れて膝をついた。紅に染まった銀の輝きを抜きさって、倒れる男を避けながら、ポーラは血糊を払った。
「レイ、シーア、無事ですか」
剣を鞘に納めながら彼女は振り返る、大丈夫とレイは答えてから、はっとして背後を見た。案の定後ろに佇んでいたはずのシーアは膝を折って床に崩れていた。慌てて倒れそうになっていた身体を支える。
「御免…」
「僕こそ、気付かなくて。…しまったな、水の紋章を持ってないんだ」
「私が。もう魔力があまりないので、止血程度にしかなりませんが」
寄って膝をつく、両手を掲げて、彼女は風の魔法を唱える。ふわりと流れる風に包み込まれて、二人の傷は見る間に消えていった。
「有難う、ポーラ」
「いえ…後で先生に見てもらってくださいね」
「レイ、ポーラッ」
僅かに息を上がらせて扉を潜ってきたのは茶褐色の髪を持った少年…先程の矢を放った本人。
「テッド」
「シーアは…無事か」
辺りを見回してから、中へと入ってくる。身体中に残る刃傷の跡と魔法でも消せない赤の痕を見て顔を歪めるも、まだ意識を保っていることに安堵したようだった。彼の後ろから、兵たちがひとりふたりとやってきた。中に蒼い外套を纏った青年が現れる。
「遅れてすまん、しかし…凄いことになってるな」
「すいません…」
「いや、謝ることじゃないだろ。部屋を移さなきゃならないか」
「フリックさん、あの」
「ああ、悪い。少しだけ待っててくれな」
続けようとした言葉を遮るように、フリックは言い捨てて部屋を出て行く。言葉を紡ごうとしていた口を空けたまま途方に暮れるシーアに、レイは苦笑を浮かべた。
「レイ…」
「シーアの言いたい事は、前の事であいつもお見通しって事だよ」
「…」
「なにやったんだよ、お前」
何となく想像は出来ているらしい、じろりと睨んでくるテッドにシーアは視線を反らして俯いたが、ふと何かを思い出したのか、目を瞬かせて顔を上げる。
「そういえば、二人とも…どうしてここに?」
「え」
「二人はグレッグミンスターに行ったんじゃ」
ああ、と二人は視線を交わして、曖昧な相槌を打った。かりかりと頭を掻いて、テッドが口を開く。
「あれな、嘘」
「…へ」
「実はさ…同盟軍はもう前から、不審人物がうろついてるのは掴んでたんだ」
「それを、彼らはランを狙う者だと思ってて。つい先日動きがあったから、彼を護るために水面下で警戒をしていたんだ」
寝耳に水だと言わんばかりに眉を潜めるシーアに、二人は苦笑した。レイもテッドも、長い間立ち歩くことも出来ない身体であろうとその話を聞けば無理に動き出すだろうと思って態と告げていなかったのだ。その予想は外れていなかったようだ。
ポーラにしてみれば予想していたところはあったのかもしれない。微かに表情を曇らせたが、それだけに留まっていた。
「あまり表沙汰にも出来ないし、軍内で大っぴらに言えないものだったから俺達に白羽の矢がきたって訳だ。
だけど…シーアの方だったなんてな」
予想しとくべきだったと、顔を顰めるテッドにシーアは首を振った。
「僕も、まさか街の中、しかも表側で来るとは思わなかった。
…彼は、前に逃した人間だったんだ。」
「窮地に追い込まれた末…ってことか」
「…多分」
ふうと息をついて微かに俯く彼に、ポーラが静かに声をかける。
「疲れましたか」
「御免、少し…」
「休めって言いたいところだが…傷の手当てしてもらわないとな、まず」
「いや、大丈夫。ポーラに魔法をかけてもらったし」
言った途端、三人が一斉にシーアを諌め始める。
「いけません、傷口を塞ぐ程度にしかならないと言ったでしょう。ちゃんと手当てを受けてください」
「莫迦かお前はっ。そんなことをしてるから傷の治りが遅いんだ、一箇所に留まってるときぐらいちゃんと治してもらえッ」
「シーア、駄目だ。それでなくても身体の調子が戻ってないのに、放って置いたら何を併発するか判らないよ」
「………」
一斉に叱られて、身体を縮めたシーアは眼を瞬かせた。ちら、ちらと、今にもまた捲し立てそうな三人を恐る恐る見上げる。辺りの兵達が見守る中、暫くの沈黙の後、一人が重々しく口を開いた。
「シーア」
「…はい」
「行くぞ」
「…」
「返事」
「…うん」
テッドの有無を言わせぬ口調に、シーアは項垂れた。
(2…いつ頃にするか考えてない)

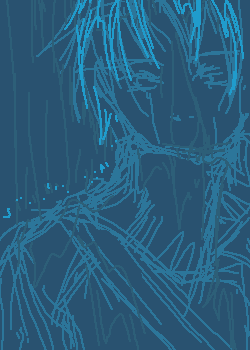
それは酷い雨の日
「その時期は丁度雨が続く時期でね。
私の前に現れたときには既に雨に打たれてずぶ濡だった。
心がそのまま姿にあらわれたように、頭の天辺から足先まで。
それどころか顔色も酷く悪かった。恐らく眠らずに来たのだろうと思ったよ。話は既に、届いていたから」
「絶望の只中にいるというような声で、暗闇しか見えないというような虚ろな眼で、彼は私を見た。
そして言ったんだ、今にも泣き出しそうな顔で」
「…喰われたと、嘆いていたんだ」

がくん、と靴底が階段を踏み外したと同時にバランスが崩れる。辛うじて支えていた身体が地に落ちるのを防ぎきれず、咄嗟に腕で頭を庇う。鈍い振動が腕に伝わってきた。
「――ッ…」
のろりと、身体を起す。壁に片手を添えて立ち上がろうとしたが、右足に鈍い痛みが走り、おまけに力が入らないことを知って諦める。詰め込んでいた息を吐いて、上半身を上げた。
顔を上げれば、光射す出口が。
下ろせば、闇に紛れて蠢く獣の気配が。
「…」
痛む身体に鞭打ちながら、シーアは階段に座り込む。そうして闇を見る姿勢をとった。届かぬ光を背にして、闇の中に煌めく赤い星を見つめる。
二本の剣は、先程の戦闘で足止めとして置いてきてしまった。唯一あるのは、彼と交換した短剣一振りのみ。けれど今の身体はそれすら振るえないだろう。何しろ立ち回るのに肝心な足が片方、もう力が入らないほどに噛み砕かれていたのだから。
だから、あと少しで光に戻れるという所まで来た事に。
背を、向けた。
手袋で覆われた左の甲を、右の掌で撫でる。
(先導したテッドが戻ってくるまで、まだ少し掛かるだろう)
彼はきっと後ろを振り向かない。それ程の信頼は得ていると、最近ようやっと思える様になった。だから自分が辿れるように道を開いてくれているだろう。
(…アルドとポーラは、きっと無事に戻っている)
抜け出す途中で離れ離れになってしまったが、二人の力は自分が良く判っている。もしもの時の為の応援を頼んでいたし、連れていた者達の無事を最優先にとも言っていたから、その命はきっと違われてないだろう。
(…なら)
思う。この左手に宿る力を、放ってもいいだろうかと。
こんな辺境だったら命を失っても噂が広まる事はない、次の隠れ蓑を立てる時間はあるだろう、そして厄介な紋章もこの地下でならば封印されるかもしれない。
今ここで放てば、石造りの地下迷路は砕け落ちる。自分自身も埋まり、周囲は近寄る事が出来ない状態になる。こんな都合の良い条件は、そうそうないだろうと思った。
けれど、
『死ぬな』
そういった彼の言葉を、思い出す。
『…頼むから、俺の前では』
ここで生き埋めになっても、彼は自分がいなくなったと思うだろうか、そうなら自分は約束を違える事になる。それはこれからも長い月日を生きる彼にとって、酷い仕打ちではないだろうか。
(約束は、護りたいな…)
苦笑を浮かべて、目の前を見る。
としゃりと赤い液を滴らせながら一歩、獣の足が近付いてくるのが見える。
此処まで来れば、罰を使うが使わまいが同じ事ではないだろうか、使えば罰に、使わなければ目の前の獣に喰われて終るだけで――
ふと思って、懐を探る。指先に当たって出てきたのは一振りの短剣。だが、この状態で何が出来るというのか。
(でも)
生きようとしなければきっと。
(皆に、叱られてしまう)
それだけ、それだけの為に。
たん、と獣が音を立て跳躍した。一歩、二歩、天井ギリギリのところまで飛び上がった身体は、自分目掛けて落ちてくる。
たった一度、それも確実に急所を当てねば終る。シーアは短剣を構え、獣が落下するのを待ち構えた、その時だった。
光射す出口が一瞬にして闇に染まる。その闇が這いずる様に、しかしあっという間に獣に纏わりついた。獣は空で身体を捩り闇を振り切ろうとしたが、うめき声をあげて失速し、シーアの目の前で倒れた。それから、ひくりとも動かない。
「無事か、シーアッ」
何時の間にか消えていた光が戻ってきている事に、かけられた声で気付く。そして一瞬の闇の正体を、聞えた声で知った。
(…嗚呼)
肩を落とす、使わせてしまったのだと、思った。
(4中。シーアが戦時中に生きようとしていたのは、こんな声もあったからではないかなと)
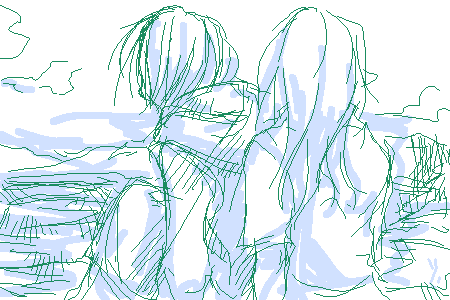
「湖が好きなのか」
かけられた言葉に、彼女は振り向いて答える。
「湖というよりは…海ですね。私達の生まれ故郷は島でしたので」
「そうなのか。…それで、どうなんだ」
「湖に興味を持つほどには意識を外へ向けられるようになっています。まだ暫くかかりそうですが」
「そうか、でも、いい傾向だ」
朗らかに笑う男に、そうですねと彼女も微笑んだ。
さらり、と衣擦れの音を立てて隣の少年が振り向くのに二人で気付く。同時に見れば、少年はぼんやりとした表情で二人を見つめていた。目を瞬かせて、交互に二人の顔を見て、最後に女性の方へ視線を向ける。
「ポ、ラ」
「はい。ポーラですよ」
微笑んで頷けば、少年もやんわりと口の端を上げた。ふうん、と様子を見ていた男が感嘆する。
「笑う様にもなったのか」
「そうみたいですね…シーア?」
呼びかけた少年は、じっと男を見つめている。何処か探るような目つきに男は一瞬身を引くも、すぐに笑って顔を近づけた。
「よう、シーア。俺が判るか? ハルモニアでお前が助けてくれたんだ」
こくん、と頷いて口を開く。あ、と音を出すも、それから続かず、視線がさまよい始める。どうしたのだろうかとポーラが首を傾げていると、あ、と今度は男が声を上げた。
「そういやちゃんと自己紹介していなかったな。俺はイグニスという」
「イ、グニ、ス」
「そう、イグニス。 彼処ではありがとな。本当に助かった」
ゆるりと首を振るシーアに、イグニスは笑って彼の髪をかき回した。
(炎の英雄戦争なんですなんて言ってみる。なんでこんなことになってるのかは…多分追々)