
どうん。
土の魔法に護られて、騒音をたてながらそれ程の衝撃もなく地に降り立つ。
砲のある丘、その真中。ぐんと矛先が己に向けられる。
光が溢れる前に、彼は立ち上がる。そして左手を掲げて、
「罰」
紡いだ。
「…償いをしよう」
赤黒い光が溢れると同時に、悲鳴が響き渡り、鳴動した。
(ラプソディアのやりたい放題)


「シーアさーんっ!」
ぱたぱたとかけて来る音と、聞きなれた少女の声に振り返る、途端シーアを抜かした殆どがひたりと身体を硬直させた。
「ナナミちゃん?」
「みてみて、新作っ! 今日シーアさん起きてるって聞いたから、がんばったのっ」
言いながらどんと音をたてて、持ってきた皿をテーブルに置くナナミ。
テーブルに置かれたのはなんともいえない毒々しい色の皮をした――
「シーアさん、好きなんでしょ! わたしの作った味、どうかなあと思って」
…饅頭だった。
すごいものがきてしまった、とシーアを抜かす一同が思う。
酒場に集まっていた殆どのメンバーがナナミの料理を経験済みだったらしい、きょとんとその物体をふしぎそうに見つめているのはシーアのみで、後は殆どが冷や汗を流していた。
「…シーア、やめたほうがいい、きっと胃に来るよ」
ぽつりと呟いたのは、いつの間にか後ろに来ていたルック。彼も珍しく顔を青ざめて頬を引き攣らせていた。それに同意するのはポーラ。言葉こそないが、視線を合わせればやめてくれ、と必死に訴えていた。
「うん、まだ起きたばかりだし…後で、食べさせてもらった方がいいと、僕も思うよ」
出来るだけ声色を普通に出そうとしているのはレイ。表情も普通を装っているが、彼もまた微かに青ざめていた。後ろで小さくクライブもそうしろと呟いている。
「ええー…でも、お饅頭ってつくりたてが一番美味しいって言うじゃない?」
「ナナミ…シーアさんはまだ病人なんだから、無理強いは駄目だって」
むうと頬を膨らませて渋るナナミに、ランが苦笑交じりで告げる。彼だけが唯一ナナミの料理を真顔で食べられる人間だが、近頃漸く他の人間には脅威となることを学んだ。
兄弟に諭されてしゅんと肩を落とすナナミを見、一同がほっと胸を撫で下ろした時。
すうとだれかの手がひとつの饅頭を掴む。
ぎょっとして見やれば、シーアが間近で饅頭を向き合っていた、そして徐に皮を割って中身を見る。ふわりと香ばしい、良い匂いが溢れてくる(とてもそれが曲者なのだが)。
「し、シーア?」
恐る恐るレイが名を呼べば、彼は返事をかえさずに欠片を少し口にした。ざわ、と周囲がうめくような悲鳴の様な声を上げた。
それから暫し、数秒。
「………」
「…」
「…」
「…」
「…」
「…」
「ね、どう?」
固唾を飲んで見守る中、ナナミは嬉しそうに彼の顔を覗き込む。彼はゆっくりと咀嚼した後飲み込んで、目を数回瞬かせる。
「…ナナミちゃん」
「うんっ」
「味付けって、どんな風にしようと思って、つけてる?」
何を言い出したのだろうか、というか何ともないのだろうか。
早鐘を打つ胸を押さえながら周囲が彼を凝視する中、シーアはナナミの答えを待っていた。彼女はうん、と頷いて、
「ええとね? まずは普通のお饅頭に、次は肉まんの味が来て、それからトリガラのスープ、でお漬物がきてキムチが来て…」
どんなんだそれは。
心で突っ込みつつというかそんな味付けをしようとしていたのかと皆が思う。シーアは真剣に彼女の話を聞きながら頷いて口を開いた。
「つまり、その味が次々に味わえるようなものがつくりたかったんだね」
「…出来てなかった?」
首をかしげて問い掛けてくるのに苦笑しながら、シーアは僅かに言葉を濁す。
「…僕の口ではちょっと、判らなかったな、御免。たくさん味わうよりも僕は、ひとつの味をちゃんと食べたいから。多分皆もそうだと思うよ」
「そっかー…」
しゅんと肩を落とすも、ナナミはすぐに顔を上げてにっこりと笑った。
「うん、判った!今度はちゃんとひとつの味を作るねっ。有難うシーアさんっ」
「こちらこそ、有難う」
えへへ、と笑いながら彼女は走り去っていった。…またつくりに行くらしい。
嵐の去った酒場に沈黙が訪れる。じりじりとした空気が流れていた、皆動いていいのか悪いのか判らず、周りを見回している。
「…シーア、大丈夫ですか」
ようようとポーラがきいてみれば、彼は唇に親指を当てて何か考え込んでいる様子ながら微妙な相槌を打った。
「…ん…なんというか、ラン、ごめん」
「いいえ、ナナミの料理は凄いものなんだって、わかってますから」
うん、と申し訳なさそうに笑って息をつきながら椅子に背凭れる。
「凄いな…料理の材料で、ここまで出来るなんて」
「シーア?」
眉間に皺を寄せてレイが訝しんでくる。彼は些細な違和感に気付いたのだろう、シーアは苦笑しながら視線を一度だけレイに向けて、戻しながらため息をついて。
「…舌が、麻痺しかけて呂律が回しにくくなってる」
『……………………』
絶句。
「おまけにちょっと、身体の中も段々…っ」
更に苦笑を浮かべたシーアの面持ちに、少しだけ苦痛が漏れる。腹を押さえて前のめりになっていく身体に一瞬理解できずなにがおきたのか見ていただけだったが、一番早く気付いたポーラがシーアの身体を支える。
「シーアッ」
「誰か、先生をっ」
「ああもう、だからやめておいた方がいいって言ったんだ…!」
「おい、しっかりしろ」
「…ら…」
「大丈夫じゃないでしょうっ!」
騒がしくなった酒場の声は届かなかったらしい、その後もナナミは嬉々として調理場に立っていたという…。
その後、ナナミの料理の回避法に関しての資料が作られて被害は大分減ったものの、それでもごくたまに被害者が出たとか出ないとか。
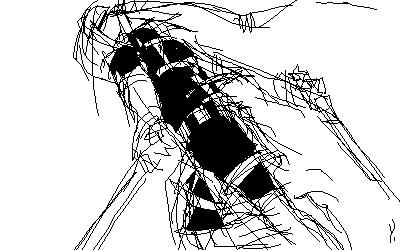

一緒に行こう
(動物シリーズ)

「…テッド、オヤバカって言葉知ってる?」
「知ってますとも!」
自覚済み。(末期)

掌の上でなぞる様に彼の舌が這う。手首まできた赤の雫を掬い取りながら、雫が溢れ出す傷を舐められる。痛みと共にぞら、と背に訳のわからないものが走って下がろうとするのだが、如何せん手を繋ぎとめる彼の腕の方が強かった。
テッド、と呼びたかったが、声を出せば素っ頓狂な声になってしまいそうだったので口は閉ざしていた。
(ちょっとこれは…)
冷や汗をかきながら、
(きもちわるい、というか、…こわい)
今更ながらなんでこんな事になっているのか、と問われてしまえば今のシーアには成り行きでとしか答えられないのだが。
ゆるりと影が遠のく、見れば、テッドが口元を押さえて離れていた。彼の面持ちも何処か曖昧な色を乗せている…
「…で」
「で…」
「なんか、あったか」
無言でふるりと首を横に。だよなあ、と口元を拭って、苦く笑う。ははと空笑いを響かせて、
「………」
「………」
微妙な空気が広がって、二人どちらともなしに視線を反らした。
「…すまない、シーア」
「いや、いいんだけど」
「…あー、莫迦だな、俺」
くしゃりと髪をかき回して、寝台に仰向きに倒れるテッド。深いため息をついたのにシーアは苦笑した。
「作り話だったのかもね、僕も紋章について少しずつ調べていたけれど、そんな話は一度も聞いた事がなかった」
「あんにゃろ〜…」
ぎりぎりとうめく彼に笑う。じろりとシーアを睨んでから、テッドは今度はかるく息をついた。
「でも、俺もどうかしてる。血を交わしたくらいで、繋がりなんか出来る訳ないんだよな」
「なんで、交わしてみようなんて思ったんだ?」
ちら、とシーアを見、天井に戻す。暫しの沈黙の後にテッドは徐に己の右手を掲げた、剥き出しになった鎌の様な痣のある右の甲。
「そういうものでもあれば、少しでも『これ』がいいものに見えるかなと思ったんだ」
「…」
「ソウルイーターは、俺にとって形見のようなものだし、大事なものでもある、と思う。
でもやっぱり、それだけじゃないんだ…したくなかったけど、再確認した」
「テッド」
名を呼べば、彼は視線を合わせてくる。に、と笑ってテッドは寝台に転がったまま両の掌を重ねた。
「悪いな、付き合せて」
「…意外にテッドは迷信深いんだって知ったから、良しとするかな」
うるせ、と言いながらそれでも彼は笑っていた。向けてくる右の拳に、シーアは左の拳で応えた。
翌日の昼頃だろうか。ギルドへ立ち寄った帰りにシーアはふと気付いて足をとめた。
(しまった、次のギルドの仕事は、レイとテッドも来るって言っていたっけ)
二人の駄目押しで、最後まで渋っていたグレミオをも落とし、外へいけると喜んでいた二人を思い出す。だから次は何が何でもついていくと宣告されていたのだ、だが、今受けてきた仕事はレイはとても連れて行けないレベルのもので。
(…どうしよう。先に終えられればいいんだけど、僕とポーラだけでは数日かかるし)
元々近くの村の依頼で、其処で暫し滞在する予定だったのだが…そこでふと、彼の存在を思い出す。
(テッドが来てくれれば)
魔法に関して自分たちの中でエキスパートの域に入る彼がいれば、もっと早く事が運べるだろう。まずは話をと思い、彼が今何処にいるのかと踵を返して。
「…?」
ふと、
違和感を感じた。
感覚の赴くままに足を進めていく。細い路地を進み離れの広間を通り過ぎる。そして曲がり角で、シーアは足をとめた。何となしに進みたくなくて、でも恐らく、多分。
恐る恐る一歩をすすめて、彼は曲がり角の向こう側を見る。
其処にいたのは、渋い表情を顔に張り付かせ棒立ちになっているテッドだった。
「…」
「…」
「…あー」
頭を抱えて、テッドは徐に指をあらぬ方向に差す。
「十分、暫くうろうろする。それから」
「…うん」
主語を伝えず、そして聞かず二人は踵を返して路地を歩いていく。うろうろと、本当にうろうろと何処にいくとも考えず、きっちり十分。ひたりとシーアは歩みを止めた。
「…」
そして再度、徐に歩き出す。迷う仕草ひとつせずに真っ直ぐに歩いていき、そしてさほど時間も経たず。
テッドと再開した。
「…」
「…」
「…」
「…」
「…」
「…」
「…まさか」
「…」
「本当だったなんて…な」
「…」
「…」
それ以上出てくる言葉がない。どちらともなく、深いため息が漏れた。
(書いてから、非常に恥ずかしくなってこれ使うかいまだに迷ってるネタです… 汗)