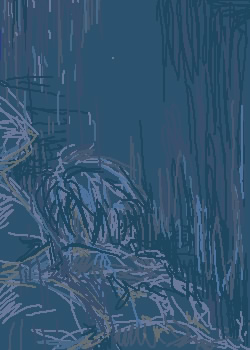
隠れるために縮めた身体が震えている。
雨に打たれた所為ならば、身体中の傷の所為ならばどんなに良かっただろう。
けれど違う、この震えは、みっともないほどに恐怖からくる震えだった。
あの悪夢から三百年近い時が流れたというのに。
「…畜生ッ」
小さく、己に叱咤した。
石畳に溜まった雨が跳ねる音が幾重にも響いたのに息を潜める。音が過ぎ去るのを待ってから、彼は息を吐き出した。
癖で行なっていた路地裏を歩き回る事が結局は役に立ってしまった。完全に追手を撒いた、けれど、そこで身体が崩れてしまった。
ざらざらと雨が降っている。冷たい雨が、赤い雫と共に石畳に落ちていく。
逃げなくては。そう思う、けれど、何処に。
そう考えが過ぎった瞬間に口の中にどうしようもない苦味が広がる。
頭に思い浮かんだのは、ふたりの存在……ほんの少し前ならば一人も思いつかなかったというのに。
莫迦だと、自分を叱咤する。誰にも縋らぬ様に生きて来たはずなのに、一人で生きていた筈なのに、助けてと言える存在が居た事に酷く安堵している。そして同時に、二人に助けを求めてはならないと必死に叫んでいる。
駄目だ、駄目だ。自分に言い聞かせて立ち上がろうとする。けれど出来なかった、あまりにも暖かくて優しかった、残酷な一面も垣間見せたがそれでも今迄の人生で、自分の一生の中で、
一番、暖かかった。
「…」
はら、と熱い雫がひとしずく、頬に伝っていく。
脳裏に駆け巡る二年の歳月、莫迦みたいに笑って、怒って、時には苦しんだり哀しんだりもして、それでも莫迦みたいに楽しく生きた。後にも先にもないだろうと思う程の幸せな、…幸せな記憶に苛まれてしまう。
「…かえりたい」
あの暖かい家へ、優しい時間へ。
ゆるりと身体を起こす。壁を伝って足を引き摺りながら、一歩また一歩と、足を踏み出す。
ただただ、帰りたいと、心の中で繰り返しながら。
(マクドール家というのは、彼にとって最初で最後の安息の場だったのかなと)



そうと知られないように、実はいつも同行する仲間がシーアを囲むように護っていればいいなんて
…頭の片隅すら残ってないことがあるんですが、でも4って4主自体が狙われてもいるんですよね…
なんて呟いてた板。

ひゅんと剣を振って、付着した赤い液を落とす。それからゆるりと振り返ってみる。
異形の姿をした生き物が足元に転がる中に佇むひと。月明かりに照らされて、闇と紅に身を染めていた。
視線に気付いたのだろうか、ゆると振り返って、彼は目を合わせる。
ああ、やっぱり。
それは時折かすめる様にみたものだ。数年前に常に見せていた露草の色のはずなのに、どこか濁った、灰がかったあお。
鈍いあかをからだじゅうに散らばせながら振り返った彼は無表情だったけれど、その振り返るまでの瞬間、かれは、
わらっていた。
「…お怪我はありませんか」
窺うように聞いてみれば、言葉なくただこくりと頷く。態度で示すのは昔からの癖でもあったが、何故だか今の彼が行なうと僅かに違和感が残った。
一瞬戸惑ってから、目の前まで寄る。血糊をふるって剣を鞘に納めた彼は、目の前に来ても呆然と佇んだままで。周囲の状況も己の姿も、戦いが終ったあとそのままなのに、全てをみていない様子を見せた。せめて顔の汚れだけでもと、小さく失礼しますと告げてから布を取り出して頬を拭った。その行為すらもされていると気付いているかどうか。
ぼんやりと、見せたことのない呆けた面持ちで、そろと視線を向けてくる。
「ミレイ」
「はい、なんでしょうシーア様」
僅かに口の端が上がる。
「もう僕は、シーア様ではないよ、ただのシーアだ」
「…すいません。癖で」
前々から言われていたことに慌てると、くすりと彼が笑う。その面持ちが何故か、ひどく辛そうに見えるのは気のせいでないのだろう。
「…無理しなくて、いいですよ」
目を瞬かせて、シーアは彼女を見る。そしてひとつ息を吐いて、言葉なくこくりとまた頷く。
「御免」
「シーア」
気にしないでとも、疲れているのだと話をそらす事も出来なかった。してはいけないと、無意識に感じていた…きっとここでそれを為してはいけないと。
だから言葉を留めて、じっと待つ。
ゆるりと呼吸を一つして。
「僕は、君に甘えている」
「…甘え、ですか」
「君に見せても、君は悟って誰にも告げないと思ったから」
「…」
それは今の状態のこと、だろうか。それとも最近になって周囲の人間も勘付き始めてきたことの方だろうか。
「…少しずつ」
ぽつりと、彼が呟く。
「自分がなにを見ているのか、わからなくなってきてるんだ。
同時に何かに急かされているようで、気付いたらこんな風になっている…みたいだ」
自分でも自分がわからない、と笑うように呟くも、表情にそれがあらわれてこない。
…前から、様子がおかしいと感じていた。あの件以来、時折ふらりと消える姿に不安を感じていた。
それはきっと、今は離れて生きているあの女性も同じだった筈だ。
「…確かに私は、あなたのことに気付いていました、けれど、まだ誰にも話した事がありませんでした。
けれど、…シーア。」
一瞬言い澱むも、ミレイは言葉を紡いだ。
「ポーラには、告げた方が良いのではありませんか」
「出来ない」
かえってきた言葉は簡素で、しかし切実な色を乗せていた。
「彼女はいま頑張ってる、なのにこの事を告げれば何もかも捨ててきてしまうだろうから。」
「けれど、そうしなくとも、彼女は気付きます。私が気付いているのですから」
「…」
僅かに眉を潜める。ほんとうにささやかな感情の揺れ。
「今は彼女はいません。だから気付かれないでしょう、けれどいつか他の誰かが気付く。それはきっと彼女に届くでしょう。
それはシーアも判っているのでしょう?」
暫しの間を置いてから、かすかに頷く。
ふと違和感に気付いた、そうだ、彼は態度で示すことは多かったが、けれど口数が少なかったわけではない。だが今の彼は、言葉が極端に減っていたのだ。
共に同行する者たちといる時と今の彼の姿に違和感を感じたのだ。
「…今は誰にも告げません。私の小さな力ですが、援護します。
だからこの旅が終ったら…彼女と話をしてくださいませんか」
暫しの沈黙が落ちる。
錆臭い匂いが充満する闇の中で、沼に足をとられて硬直してしまった様だとミレイは思った。
彼はこの中を、一人で歩いてきたのだろうか。
「…そう、だね」
ようようと言葉が出てくる。肩を落として、掌で顔を覆う。
「本当に…」
どうしたのだろうと、弱々しく呟く。弱りきった姿に手を差し伸べようと腕をあげるも、ミレイはひたりと動きを止めて、そして下ろした。
彼を抱いて宥める事が出来る腕は、自分の腕ではないのだと判っていた。
(無口設定だったりします)

仕事を終え今日は親友の家で夕飯をご馳走になる約束をしていた彼は、意気揚揚とかの家の扉を潜った。それまで頭の中は今夜の夕飯のことでいっぱいだった、いっぱいだったはずだった。
扉が開いた途端に見えたものに、全ての思考が奪われた。
忙しなく召使が行き来する中、ちらちらと珍しそうにみられているものがひとつ。廊下の途中、飾り棚の脇に縮こまりながら俯くひとのかたちをしたもの。とてもとてもそれは、みたことのあるもので。
それを理解するのに十分過ぎるほどの時間を要してから、彼はふかくふかくため息をついた。のろのろと寄り膝をおって、呆れ混じりに言葉を発する。
「で、なにしてんだよ」
声が届いたか、のろりと顔があがる。…泣く寸前の顔だった。
「…そうじ」
けれど次に出てきた言葉にあからさまには? と聞き返してしまった。ますます肩を落として俯く彼にしまったと毒づきながら、頭を掻きながら何を言いたかったのかを考える。
…まあ彼のことだから、なにをしようとしたのかはすぐに判るのだが。
「掃除をしようとしたんだな? 厄介になってる御礼かなにかで」
是と頷く。
「そしたらグレミオさんがとめたんだな」
頷く。
「口論に…いやお前今話すの苦手だから、一方的にとりあげられた」
こくりと。
「グレミオさんのことだから客にそんなことをさせてしまっては自分の恥だとか、言ったんだな」
しばしの沈黙のち、是。
「……………………で、反省中か」
しゅーんと、擬音があらわれそうな程に項垂れた彼に、テッドはふかくふかくため息を再度ついた。つむじが見える頭をぐしゃぐしゃにかきまわしてやる。
「ちゃんと恩をかえしたいなら、他の事にしておけ。お前もこっちのことではエキスパートだけど、この家ではグレミオさんに勝てる人なんかいないんだって」
「…」
「あんまり気にするな。久し振りに人の中にいて、少し疲れてるんだろ、お前」
その言葉を一瞬理解出来なかったのか、顔をあげて目を瞬かせて、考えるように首をかしげた。思わず笑ってしまったのに、彼がなに、と視線をむけてくる。
「…お前って面白いよなあ」
見飽きない、と呟くと、心外だといわんばかりに眉を寄せて…それでもほんのささやかで、親しいものでないと気付かないほどだが…睨みつけてくる。滅多に見せない仕草に笑いがこみ上げて、思わず頭をよせて抱き締めた。
「ほんとなんかもー、ここに来てからお前まるくなりすぎ。ええい愛いやつめっ。」
「っ、っ、−−−っ」
驚いているらしい、じたばたともがきながら逃れようとするのを無視していてると。
「…新種の苛め?」
「あ? 心外な言葉を聞いたなあ」
「そうとしかみえないって」
階段越しに見下ろしてくる姿がひとつ。やめとけば、と忠告はしているものの、声色と表情は一致していなかった。
「終ったのか、レイ」
「ああ、今先生が帰られる」
そしてついと目が上がると、厳しい面持ちの壮年が降りてくる。侮蔑の視線を向けられたがテッドは笑って会釈すれば、彼は無視するようにこちらから視線をそらした。通り過ぎたあとでレイが済まなさそうに視線を向けるのには肩を竦めて笑ってやった。
玄関でひとことふたことの会話の後、帰っていくのを見届けてからテッドは動かなくなった彼の頭を抱えていた腕を離す。ふう、と彼は息を深く吐いた。
「…で、なにしてたの?」
戻ってきたらしいレイが、テッドの隣で彼と同じく膝をおって様子を見ている。というかシーアはここでなにをしてるのと問い掛けてくる辺り、彼は何も知らなかったようだ。
「たいしたことじゃないさ。ただ掃除が出来なくて拗ねてただけって話」
「…掃除が出来なくて拗ねるって何があったの」
「それはまあ、複雑な事情があってだなあ」
「テッドが面倒なだけなんだろ」
ばれたか、と笑えば、親友がつついてくる。と、そこに奥から声がかかってきた、グレミオの声だ。
「おっと、じゃあ飯の後でな」
「判った」
立ち上がって先に行く彼を見てから、テッドは座ったままのシーアの腕を引いて立たせた。戸惑い気味に力に従う彼に、今度は苦笑が漏れる。
「おまえもだ。グレミオさんはお前も勘定にいれてるぞ」
「…」
「行こう、シーア」
ほんの少し引けば、彼はのろりと従って歩き始める。一応後について来る姿に安堵しながら、テッドは彼らが待つ場所へと向っていった。
(無口設定)

「おーおーすげー」
「…相変わらずだねシーアは;」
「シーア…そんな意地にならなくても;
使えなくても生きていけますよ…」
「そうだよ、俺だってうまく使えないし」
「でも一度立ち上げれば何もしてないのに必ず一度はフリーズするのはもはや芸当だよな」
「………………………」
(…現代設定?)