
身体の一部が熱い。溢れる様にそこから熱が、痛みになって広がっていく。
なんて莫迦なことを。
そう思った、本当に、本当に。
無意識の行動だった。
「…テッド?」
青ざめた、かすかに震えた声が聞こえる。それに応えることもできず、ずると背から何かが抜けたのを切っ掛けに徐々に身体の力が失っていき、凭れるように背に身体を預けた。
何処かで悲鳴が聞こえたような気がする。凍るように止まっていた周りが慌しく動き始めた。
「…るさい、騒ぐな…」
「テッド…ッ」
「これくらいじゃ、死なない…けど、」
紋章が。
音もなく口で告げると理解してくれたらしい、彼が垂れ下がっていた右手を握り締めてくれた…左手で。
こんな状態で気を失えば、自分を失うと察したソウルイーターが暴れ出すかもしれない。そうなれば自分は制御することも出来ず、自分を生かすために周りの魂を喰らうだろう。それを阻止出来るのは、此処には彼の持つ罰の紋章以外にない。
(嗚呼)
莫迦だと思う。護るために傍にいるはずなのに、結局は彼に護られているではないか。少しでも彼が紋章を施行せぬ様、彼を護る様、傍にと。
だから彼を狙う輩を見つけたまでは良かったものの。
今日に限っていつもならば姿を見せぬが傍にいる忍の者がいない、今日に限って常に懐に持っていた短剣は鍛冶屋に預けていた。魔法を紡ぐには遅すぎる、弓を使うには近すぎる。合間を縫ってその刃を手折るには時間がない。
…気付けば、身体が動いていた。
(何を、そんなに…)
必死に、なっているのだろうかと思い。
(…そんなの)
既に答えが出ていた事を、思い出す。
ぎう、と手が握り締められる。
「テッド」
確りとした声が聞こえて、彼は無事なのだ、と安堵の息が漏れる。
今の自分の姿はかなりみっともないのだろうが、無事であればいいと心で呟き、身体の力を抜いて、テッドはそのまま意識を落としていった。

子供時代は大変だったのではと思います

「お前はよくこの高さから飛び込めるな…」
「そうかな? 気持いいと思うけれど」
「ていうか、叩き付けられないか? この高さだと」
「…」
「おい」
「…え、と。ギリギリ、かな?」
「…」
「…」
「…」
「…」
「…シーア、そこに直れ」
「はい」
(そして説教が延々と繰り広げられる)

目の前が真っ暗な気がする。けれどとても明るいような、まぶしいような気もする。
意識もはっきりしているようで、混濁している。様々な感情に押し潰されそうで、体が動けない。
ぱたり、
音がして、のろのろと視線を足元に移す。布の中から滲み出てきた赤い雫が、床石へ落ちていた。
ぱたりぱたり、
いきていたころの証が、
ぱたり、ぱたり、
…まだ自分は、握り締めたあの強張った掌を覚えている。
嗚呼。
何てことだろう。あんなに、あんなに護りたいと思って戦争を駆け抜けたのに、戦争が終った後で、こんな。
感情が溢れ出して、目の前がぼやけてく。きつく目を閉じながらシーアは、俯きながらうめくように呟く。
「…御免」
まもれなくて。
「シーアッ」
聞きなれた音に名を紡がれ、のろのろとシーアは顔を上げる。居る筈のない存在に少しだけ驚きながら、目深く被ったローブ姿の王を見上げる。
「リノさん…」
彼は注意深く周囲を見回しながら数人の共に耳打ちをして散らばせてから歩み寄ってきた。目の前で立ち止まり、呼吸を暫し整えてから彼は徐に拳を作って振り上げる。そして真っ直ぐにシーアの頭へと下ろす。がづると鈍い音が立って、シーアは殴られた姿勢のまま硬直した。
「この、大莫迦者ッ。相変わらずだな、お前は!
一人で突っ走ってどうにかなることじゃないだろうっ。」
「だけどっ、…だけど。」
急くように開いた口は、喉まで音を出しかけて止まり、勢いを失っていく。
「…助けたかったんだ」
俯いて、両の手の中にある布を抱える。リノもその包みに気付き、床下に滴る赤い雫を見て押し黙った。
「もう、遅かったけれど」
「…」
リノは深く息を吐いて、肩を落とす。そして徐に手に持っていたローブを、シーアの肩へとまわした。
「リノさん」
「なんだ」
「わがままを言っても、良いですか」
言葉なく、彼は問いかけてくる。
「…埋葬、ちゃんとしたいです。身体も一緒に」
「…判った、なんとかしてみよう」
「すいません」
とん、と彼の大きな手が頭を軽く叩く。
「…俺も一応、仲間だったからな。」
その言葉にシーアは項垂れる様に頷いた。
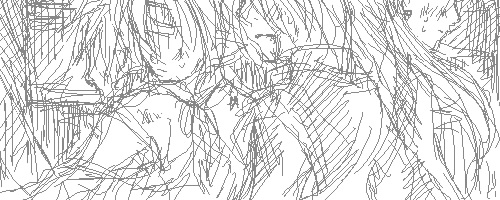
じりとにじり寄って来る気配は感じている、けれど姿は一向に現れず。
じりり。
確実に近くなる殺気、固唾を飲んで…しかし冷静に、シーアは辺りに意識を広げていく。同時に左手に宿した烈火へ向けて意識を集める。
「来るぞ」
テッドの言葉を皮切りに、気配は四散した。空を切るような音だけが響き、一瞬にして気配が目の前まで来る、その刹那にシーアは集めた力を言葉で解放した。
(描きたいものだけが確実に増えていく…(とおいめ))

(がしと後頭部を鷲掴みつつ)「…なにやってんだおまえは〜〜」
(ぐえっと蛙のようなうめきをあげたあと)「ま、饅頭…」
「開口一番がそれか」
「でも見たことなくて」
「それ以前にこの場所に見覚えがないのは判るか」
「すごく美味しそうで」
「そして通貨すら判らないのを判ってるか」
「どんな味がするんだろうなと」
「あのな、ひとつ間違えたらこれから生きてけるのかすら判らないんだぞ!俺ですら判らない通貨で見たこともないモンスターが出てしかもこの島なんて俺は知らない!飛ばした張本人もついてきてない現状を饅頭で現実逃避するなっ」
「で、でも饅頭…ッ」
「現実を見ろーっ!」
(流石についてこれないだろうと思っていても…っ(視線反らし))

なにがどうなっているのだろうか
体中が麻痺したように動かない。
ぼんやりとしているようでもあり、己の全てが張り詰めているようでもあり、とにかく全く周りが見えなくなっていた。
ただただ呆然の目の前にあるそれを凝視する。
めのまえのこれはなんだろう。
これは、あのひとではなかったのか。
どうしてあの時、自分に襲い掛かってこようとしたのだろうか。
どうして、これはうごかないのだろうか。
疑問ばかりが頭をかけめぐる。どこか違う答えを探してもいるようで、けれど、甲板に横たわるその姿が着ているものを見れば、それは決して覆されないと気付かされる。
見慣れた色、見慣れた衣服、その肌触りも、何処が解れて繕った痕があるかも覚えている。
ああ、これは、この人は。
気持が現実に追いつかない。周りが騒がしくなっている気がするが、視線が横たわるそれから離れなかった。
もうどうでもいいとも思っていたかもしれない。それくらい心が、目の前の現実を否定していた。
ぺさ、と乾いた音がした。月明かりと船の明かりのみで見つめていた姿が陰に隠れるのに、ようよう彼はのろりと顔を上げる。
そして見えたそれに、全ての感情が消えうせた。
光に照らされて浮かび上がるその姿、身体全体が鱗に覆われたそれが、巨大な目玉をこちらに向けている。
それは、今目の前に横たわる、あのひとの姿と全く同じで、そうあの人と同じく、鋭い爪を持った腕らしきものを掲げて―――
じゅん、と音がした。
次に熱と、吹き荒れるほどの痛みが身体を駆け抜ける。悲鳴を上げる間もなく身体が前のめりになった所にもうひとつ、今度は横に線が走る。小柄な身体は容易く吹き飛ばされた。
「キリル様ッ」
聞きなれた声が名を呼んだ、そう認識した直後にどう、と背が甲板へ叩きつけられる。息も出来ぬほどの痛みが走り、その衝撃で目の前が白に染まる。
そのまま彼は、真っ白な意識の奥底へと潜り込んで行った。
(ラプソディア。このイベントは衝撃でした…)