
かた。
かたかた。
かたかたかた。
わずかに目の前のカップが彼の震えが響いて音を立てている。蒼白の表情で、脂汗なのか冷や汗なのか、だらだらと汗を流しながら差し出したカップと睨み(?)あって数十分が既に経過している。
どこまでもその目の前のカップが恐ろしい、と言わんばかりに、カップを前に身体を硬直し縮こまらせている様子に、流石にレイもどう対応すればよいか迷っていた。
(…一応、一番普通に見えるのを選んでもらったんだけどな…)
効果はなかったらしい。家にあるものは、どれも一般人にとっては高価なものであるとは判っていたのだが。
ため息をついて、ちらと隣を見た。隣で恐縮のあまり震えるシーアをよそに、嬉しそうに菓子に手をつけるテッドの姿があった。……そういえば彼ははじめてきたときも、多少一度は躊躇したものの、それからは物おじしなかった人間だった。
(どうしてこうも違うものだろうな)
思いのほかじろじろ見つめていたらしい、不躾な視線に気付いてテッドがレイを見た。
「ん?」
「…いや」
「なんだよ。いいけどさ…。
…シーア?」
ひく、と体が跳ねる。
「ちゃんと飲めよ、グレミオさんが折角淹れてくれたんだからな?」
にこっと笑ったまま紡いだ言葉に、じんわり潤みがかった瞳がテッドを見る。さすがにそこまでいっているとは思っていなかったのか、一瞬きょとりとして、テッドは苦笑を浮かべた。
「シーア…相変わらずだな」
「…カップ、取り替えた方がいいのかな?」
ちょっとだけ晴れた面持ちになったシーアに追い討ちをかけるようにいや、とテッドが答えた。
「いい加減慣れないとつけこまれるからな。こいつにはこれで飲んでもらう」
「……テッドぉ…」
完全に涙目だ。
「慣れろ、じゃなきゃ暫く饅頭禁止だ」
ががーんと豪快な疑似音をたててバックに雷が落ちたようだった。くらくらと目を回している様子のシーアにあまりの容赦ないテッド。
…確かに世話焼きの癖があるなとは思っていたが。
「テッド…せめて少しずつ」
「これでも随分譲歩してるぞ?」
これで容赦しているのか。
容赦しないとしたらどうなるのかと一瞬考え、レイはため息をついてしまった。
(無口設定…)
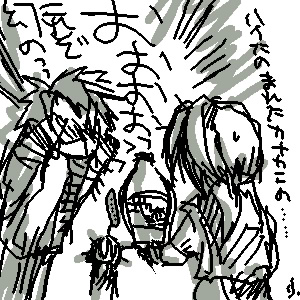
…いやあんま意味はないんですが

「きっといつか、私は貴方の手を包み込むことができなくなるでしょう」
静かに静かに、ポーラは言葉を紡ぐ。
「私が貴方と共に歩めないというのなら。いつか私が、貴方をおいていってしまうというのなら。必ずいつか、その日が来るのでしょう。
…だからこそ、いいます。
私が歩めるできる限りの時間を、貴方と共に生きていきたいです」
「ポーラ」
「置いていかれるのは、あの一度で十分です」
ごめんと小さく呟いてシーアは俯いた。

「ポーラは、人間が嫌い?」
「…判りません。幸い私が住んでいた村は皆私たちによくしてくれました。けれど恐らく私たちも、そして村の人たちも、間に一線を敷いていたと思います。
その一方でその線を踏み越えてくる人も居ます。けれど、彼らが向けてくるのは嫌悪だけです。」
「…そうか」
「騎士団の方々もそのどちらかが殆どです。ジュエル達はとても良い方々ですが…そうではない人も、います。」
「ポーラは、僕たちとどうしたい?」
「許されるなら、共にありたいと思っています」
「ならきっとポーラは人間が好きなんだよ」
「…そうでしょうか」
「僕は、そう思う。…僕は嬉しいと思う」
「…シーアは」
「?」
「人を、どう思っていますか」
「好きだと、思う。
確かにさっきの先輩たちの様な人も居るけれど…人はそれだけじゃないって、知ってるから。
僕は皆の好意で生かされていると、知っているから」
「好意…」
「君と僕らの境界線の事情は、僕はあまり判らないけれど。
考えてもいいと思う。それは無駄なことではないと思う。すぐにその垣根がなくなることはないのだろうけれど。
ポーラがそう思うなら、なくすための方法を考えてもいいと、思う」
「…有難う」
「僕は、何もしていないけど」
「私が言いたかったのです」
(会話は騎士団の頃なんですが。
特に印象的な出会いがあった訳ではなく、些細な出来事から、少しずつ一歩ずつ、歩み寄ったのが二人のイメージです)
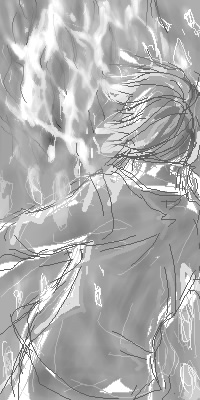
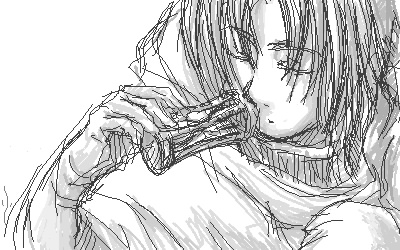

じりと肌を撫でる風が痛い。
後退りする、ゆるりと振り向く少年の冷たい表情に不様にも身が竦む。
静かに静かに、表に出すことはなく、只管奥へ閉じ込めていた憤りが体中から溢れているようだ。
自分たちが感じているもの、それは間違いなく、威圧というものだった。それも少年が持てるものでも、そこいらの人間がもてるようなものではない、きりきりと自分たちだけに向けられた鋭い刃の様な。
ぽつりと、彼が呟いて、そして。
「肉片ひとつすら残すな」
そう言葉が紡がれたのを境に、意識は消えうせた。