
表情という色が淡くしかのらなくなった面持ちに現れる笑み

テッドなら我流ぽそうですが

あなたと出会えたことの なんという幸いなことか
「シーア」
呼ぶその声は鈴のように、自分の中でちりりと響く。
呼ばれる度、微笑まれる度、何もかも吹き飛んで心が穏やかになる。
触れる肌は細やかで柔らかで、包み込まれると全てを包んでくれるような錯覚を覚えた。
じわりじわりと、溢れる想い。
そのまま縋り付いていつまでも共に居てほしいと言えたら、どんなに至福な事だっただろうか。
けれど出来ない、己が許さないと判っているが故に、
伸ばしそうになる腕を、引いて留める。
其処に居るだけで、共に在るだけで、あなたが笑っているだけで、
自分は幸いなのだと、言い聞かせる。
「ポーラ」
その呼び声から溢れる穏やかさ。
表情を強く出さない彼の優しさが、音で流れる様に自分の中に沁みこんで行く。
応えれば柔らかく笑う、つくっていない、何処か安堵した笑みに、自分もふと息をつく。
彼からは触れることは少なく、触れても僅か、ささやかに指の先だけ。
その掌を重ねて、抱き締めあいたいと願うのは、彼も同じなのだろうに。
消えぬ障害、縮まらぬ距離。
全て振り払い縋り付いて置いて行かないでと言えたら、どんなに楽な事だろう。
けれどそれは困らせるだけ、悲しませるだけ、身動きの取れぬ彼を苦しませるだけなのだ。
だから、動かず、ただ彼と共に居る。
其処に居るだけで、共に在るだけで、あなたが笑っているだけで、
自分は幸いなのだと、言い聞かせる。
(何もいうまい!(脱兎))
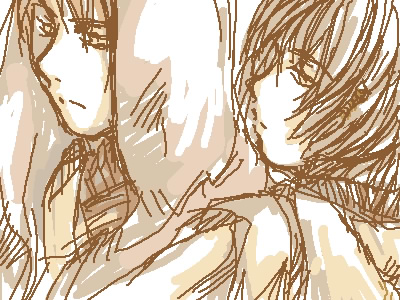
一応ジェ○イのつもりだったんだがこれだとどちらかというとシスね…(目つきが!
マスターと弟子という関係なのだからどっちかっていうとレイの方が合うのだろうがなんとなくこっちで描いてみた…(頭が暴走しております)
師弟関係に入るのならマスターはテッドなのかなーとか。でもテッドのイメージはどちらかというとアナキンだったりします…一度闇に落ちるし。(程度が違うが)
でもシーアがマスターというのもなんか…微妙だったりしたのでそれならパダワン設定だよなーと(暴走中)
嫌気が差しつつ仕事をするテッドを黙々と補佐するシーア、みたいな…… … …
なんて書いてた板。そういやジ○ダイネタはクロノでもやったな…

あんまりにもせっせと掃除するシーアにぷっつりきた模様

がづると鈍い音が響き渡った後、遠くで砂利が擦れていく音が聞こえた。続いて真横でも同じ音が聞こえて、不覚にも閉じてしまっていた目を恐る恐る開けてみる。先程はいった頭部への攻撃で左こめかみから生ぬるいものが落ちて目に入りそうになるのを手で拭って、まだ自分が立っている事を認識する。
ふわりと隣に気配を感じた、殺気をこちらに向けてこないのに訝しんで目をやれば、見慣れた外套がはいってくる。
「…え」
呆然とすれば、かすかにその背が自分に意識を向けたのが判った。こちらは振り向かず、ただ一言。
「…平気」
え、と戸惑い、それが彼の言葉で、問うている言葉なのだと気付いてから、是とこたえた。
混乱する自分を他所に突然現れた彼と、自分を狙ってきた男たちが対峙する。彼が仕掛けたのだろう攻撃で一人昏倒させているものの、あとの一人は意識が残っていたらしくむくりと起き上がっているし、もう一人無傷の者がいた。対して自分は既に立つのも精一杯で、あとは目の前に力量など計ったことのないつい数時間前に出会ったばかりの旅人だけ。
一発でのした力をみてまずそれなりには力のある人間なのだろうけれど、果たして二人を相手に立ち回れるのか。おまけに自分は己の獲物すら手元になく、完全に足手まとい状態。
(…せめて棍さえあったら)
不快な気持を払拭したくて、どうしても親友に会いたくて単身飛び出したのがいけなかった、せめて棍さえあったらもう少し立ち回れたのにと思ったが、今更そんな事でくよくよするなと自分に叱咤をかけた。今自分に出来ることは、ここからどうやって彼と共に切り抜けるかだ。
「…いのち」
ぽつりと彼が呟く。はじめて出逢った時ですらほとんど言葉を出さなかった彼が紡ぐ音は、あまり自分と変わらぬ少年のものだった。
「狙われている?」
今度はちゃんと問うように語尾が上がり、自分は是と応える。
「さっき話してたのと重なるんだけど、僕の父が偉い人だから…理不尽にうらまれることも多い。
けれど父は強い、だから…悔しいけれど、まだ力のない僕を狙って、父の血を絶やそうとする人間も、いる。父の子は僕だけだから」
それ以外にも狙ってくる輩はいる、だが今回の敵はそういう人間から仕向けられたものだろうと彼は判っていた。
自分で言葉を綴りながらも、貴族社会の水面下で行なわれる醜い勢力争いに自嘲が零れる。ほんの少し前まで煌びやかな面ばかり見ていた己が恥ずかしくなる。
少しずつ少しずつ、確実に。自分の国は衰退の一途を辿っていたと言うのに。
「…美味しかった」
小さな声、下手を擦れば聞き逃しそうな声を聞き取って、意識を現実に戻す。振り向けば、彼はこちらに顔を向けてじっと自分を見つめていた。
無表情な面持ち、だけど僅かに笑みが含まれているのは…気のせいだろうか。
「美味しい?」
「お饅頭」
一瞬何の事だと考えて、そういえば出会ったときに腹を空かせていた彼に食べさせたのだと思い出した。
胸にじわりと、斑なものが溢れる。
「たくさん、話、してくれた」
ゆるりと向きを戻したから、気付かなかっただろう。彼の言葉に、少年は顔を苦痛にゆがめていた。
ちがうと、心で自分が叫んでいる。
「おかえし」
思って。
呟いてから、たんと彼の体が跳躍した。はっと後を目で追うと彼は既に男たちの目の前まで迫っていた。待ってと叫びそうになったと同時に男がひとり剣を振り下ろしたのを、彼は剣で受け流す。そのまま滑らせて男の手元で振り払った。剣と共に赤い雫が散らばって空を舞う。既に間合いに入っていて、男の身体はがら空きだった、男も、少年も、その数秒の間の出来事に呆然とする。だが彼が上段の構えから剣を振り下ろそうとして、慌てて声を張り上げた。
「殺しては駄目だ!」
叫んでからしまったと、生死を分ける戦いの中で割り込んでしまった事を後悔した。だが彼は素早く男へ迫り、振り下ろす勢いそのままに柄を男の肩に打ちつける。
傾いた男の鳩尾を蹴り上げて昏倒させたのを見てふと息をつきそうになった刹那、横から気配を感じて無意識に飛び退いた。剣先が胸を掠めて服がはくりと穴を開ける。構えようとして、立つのも精一杯だった足が限界だと言わんばかりに力を失い、意志と反して膝が抜ける、かくりと床に落ちた身体に驚きながら、眼は迫るもう一人の男に向けていた。
再度剣を振り上げる男、しかしそれも空しく、男は目の前に現れた靴に顔をのめり込ませた。彼があの距離を一気に詰めて、男に蹴りを食らわしたのだ。
勢いに任せて一回転、外套を風に遊ばせながらふわりと地に下りる頃には、男は飛ばされもんどりをうってうつ伏せで倒れて沈黙していた。
言葉なく、少年はようよう立ち上がった状態のまま立ち竦んだ。あっというまの出来事だった…自分がどれだけ複数相手にてこずっていたのか思い出すのも嫌なくらいに。
獲物のない自分とは違い、彼は剣を持っていた。だが自分は知っている…彼がもうひとつの剣を持っている事を、その剣はふたつでひとつの役目を為す、双剣なのだということを。
…そして、彼の利き腕が左なのだということも。
すると彼の腕が上がる、赤の雫を流すこめかみに触れたのに一瞬遅れて気付き、平気だと告げる前に彼が何事かを呟いた。じわりと青い光が溢れ、こめかみの痛みが引いていく。
(水の紋章の力…)
広く出回っているものの高価な紋章を彼が持っている事に驚きながらも、有り難く思った。傷だらけのまま帰れば、家のものが大騒ぎするだろうことは判っていたからだ。服が酷い状態なのは治らないので、何かあったことは隠せないが、少しは収拾がつきやすくなる。
光が消えて、痛みも治まったのに感謝を述べてから、自分がしてしまった事を思い出して慌てて口を開いた。
「ごめん、僕は…とても危ないときに声をかけたのに、聞いてくれて。
下手をすれば貴方の命が危なかったのに…」
首をかしげて眼を少し彷徨わせてから思い当たったのか頷きひとつ、それから首を小さく横に振った。気にしないでという行動だと判ったので、ごめんと小さく呟いた。
「…むだなことだとは判っていても、彼らを僕の手で裁いてはいけない、国に任すべきだと思ったから…つい止めてしまったんだ」
国へ差し出した後の彼らの行方がどうなるかは判らない。まだ判らない、だからこそ自分が手を出すべきではないと判断した。吉と出るか凶と出るか、想像も出来ないけれど、今は国を信じるしか、なかった。
俯きかけた頭に、とふと彼の手がのる。そろりと撫でられるのに、目を細めた。
「急がない」
唐突にはじまる言葉。
「気付けるだけで、いい。少しずつ知る、それでいい」
聞き覚えのある単語に目を見開いた。顔を上げて、彼の面持ちをじっと見る。
「誠実、優しい」
君は、と言葉が続く。自分が誠実で、優しい人だと、言いたかったのだろうか。少年はそれに否と答えた。
「僕は誠実でも優しくもない、貴方に対して僕がした行動がそうというのなら、それは違う。
ただ貴方がいただけなんだ、誰かにぶちまけたくて、誰かと話がして紛らわしたくて、だから聞いてくれそうな貴方を留めるために何かを上げただけだ。そうして話を聞いてもらっただけだ」
眉を寄せて吐く言葉に、無表情のまま彼は首をかくんと傾げる。少しだけ困っているように見えるかもしれない。けれどただごめんと呟くしか出来ず、少年は益々顔を歪ませた。
「偽善なんだ、だから、気にしないで」
「…。」
ひとつ間が空く。そして次に。
「あなたの偽善は」
突然流れてきた流れる言葉に瞠目する。
「何処からが、そうなんだ?」
「どこから、って…」
「…偽善とは、自分が判断するものではないと、思う。僕を利用するための行為だったとしても、貴方と話せて、僕は、嬉しかった」
やんわりと口の端が上がる、優しく優しく、彼は笑った。
「忘れないで。」
「…」
「誠実で、優しい。だから迷う。
そうして、自分の行く道を、探して欲しい。行くべきと気付く道は、必ず見つかる」
眼を瞬かせて、彼の言葉を咀嚼して、不意に苦笑がこみ上げた。直接的なことはひとつも告げなかったのに、自分が今何で悩んでいるのかを悟っていたようだった。
…聡い人だ。そう思った。相変わらず頭を撫でて宥めてくれる彼に苦笑しながら、有難うと言った。
(シーア無口設定。すんません好き放題かかせてもらってます…)

聞こえていた足音がひとつ途絶えて、ふとレイは振り向いた。見れば、先程まで一歩後ろを歩いていたシーアが硬直して立ち尽くしている。
「シーア?」
真っ青な顔で、視線を自分より僅かに上を向いている。なにを見ているのだろうと振り向く、真後ろにあるのは自分の家と敷地と空だけ、他に何かあるだろうかと見回しても特に目を引くものはない。首をかしげてレイは振り向きなおった。
「どうしたの?」
「…、館?」
家の事を言っているのだろう、目を瞬かせながら是と答える。恐る恐る、シーアは視線をレイに向ける。
「…貴、族?」
……え?
眼を瞬かせる、いつもと違う反応に呆気にとられてしまった。
自慢ではないが自分は貴族だ、その位に見合う教養はきっちりと教育され、そして遺憾なく発揮されている(筈だ)。自分でも気付かない行動や仕草、言葉などにも現れているらしく、故に初対面でも良いところの人間だと皆気付く。
でもどうやら、彼は気付いていなかったらしい。
(商家の人間でも思っていたのだろうか)
一度も貴族の人間だと気付かれなかったことはなかったので少々楽しい気分になった。
苦笑しながら是と呟くと、徐に彼は回り右をした。そのまま脱兎しそうな勢いで一歩踏み出したところで彼の外套がびんと伸びる。首に入ったのか、蛙が潰れたような呻き声を上げる。
「おいおい、まてコラ」
その外套をしっかと掴み失踪するのを拒んだのは先程まで傍観していたテッド。顔は綺麗に笑顔を飾っていたが、声に怒気が混ざっていた。咳を繰り返していたシーアがひく、とびくついて、それからさらに逃げようとするも彼の手から逃れられない。
「おーまえ、なあ?」
突然の親友の怒りに呆気に取られている自分を蚊帳の外にして、憤りを含んだままテッドは片方の手でシーアの頭を背からがしりと鷲掴んだ。
ぎしぎしぎしと音を立てるように頭を締め付けられているようで、いたい、とぽつりと彼が呟いた。
「ただでさえ言葉足らずで誤解受けるってのに今の言い草はないだろ?
だから逃げる前にちゃんと言え、なあ?」
……あれ?
そこではたと気付く。――何に憤っているのだろうとは思っていたが、もしかしたら、もしかしないでも。
…確かに、そうやって嫌悪感を出す人間も少なくはない。現に彼と共にいたときに浴びせられたこともままある。それに彼が激怒して取っ組み合いになった事も、その喧嘩が原因でグレミオに鬼のように怒られたことも、父に説教の後何故か喜ばれたこともつい先日のようによく覚えていた。
テッドはそんな意地の悪い言葉に対して、自分の身分をわきまえつつも、自分の為に憤ってくれた。少なからずそれは、自分にとって嬉しいことだった。
(勘違いしたと、思われたかな)
確かに言葉の上っ面はそう見えるだろうし、イントネーション的にも中傷的なものにとりやすかった。けれど自分はシーアがとんでもなく無口であることは知っていたし、ただ純粋に自分の身分を気付けなかったことに驚いていたということは、ひとつ間を置いてではあるが理解できていた。
誤解を解かないとと思いつつも、つい笑みが溢れる。
彼と会えて、自分はどれだけ救われただろうか。
「テッド、いいよ。シーアのことは少しだけど判ってる。彼だってそんな意味で言ったわけじゃないんだろ?」
とりあえず止めようと声をかけると、むつと不機嫌な顔で振り向く。
「本当か?」
「…なにをそんなに疑ってるかな」
だって、とテッドは声をあげる。
「お前はそういう嫌なことは絶対顔に出さないからな」
何度呆気にとられるのだろうなと思う。表情から一気に感情の色が抜け切っただろう、反応を返し忘れて、思わず沈黙した。その間にテッドはため息をついて、それでも尚逃げようとしているシーアの外套をまだしっかと掴んでいた。
「誤解してなきゃ、いいさ。こいつはほんとに言葉が少なくて、意味が理解できる人間は滅多にいないんだ。旅の最中は結構苦労したよ」
「でも、テッドは理解できるんだろ?」
「…一応」
げんなりと顔をゆがめる、それでも随分と苦労したのだろう。
「…まあ、いいけどな。とりあえず、こいつが今逃げようとしているのは、別にお前がいいとこのぼんぼんだとかそんなのは関係ないから気にするな」
言いながら、ずるずると引き摺り出し始めた。じたばたもがく彼を容易く己の意のままにしている…。
「所でなんで逃げようとしているの?」
それよりも彼は逃げようとしていたのかという気持もあったがそれは置いといて、問うて見るとテッドから苦笑が現れた。
「…こいつさ、昔こんな家で働いてたことがあって」
「へえ」
「その時の経験ででかい家には徹底的に弱いというか…働くという事なら別にどうも思わないんだろうが、自分が客人とかで呼ばれたなんて不相応なことだと思う奴なんだよ。」
「て、ことは」
多少よいところだとは勘付いていたとしても、ここまで大きな家だとは思っていなかっただろう彼は、目の前の館を見て。
「びびったんだよ」
「………」
「でも家の皆にはもう行くって言ってるし、行かなかったら特に張り切ってたグレミオさんが悲しむだろうし、ここはひとつ我慢しろシーア」
にこにこと楽しそうにシーアにとっては死刑判決のような言葉を吐いて、ぶるぶると首を振る彼を無視し引き摺っていくテッド。
「……」
さすがにもう二の句が告げられず、レイはただ、苦笑を漏らすばかりだった。
(あとひとつ続きます…)