
あふれるもの

「あ? めっずらしー。こんな所で御守り?」(にやにや笑いつつ)
「誰の所為だ」
「俺の所為だっていうのかよ」
「お前が昨日セクハラ紛いの事をするから押し付けられたんだよっ(怒」
「だーってなあ? 気になるじゃないか」(隣を見ながら)
「なら風呂で見たらよかったんじゃないか…? あれは誰が見てもお前が悪い」(ため息つきながら)
「んなまどろっこしい」
「公共施設でやるなッ(怒」
「…にしても本当に珍しいですね。ポーラは?」
「今日はシーアについていった。あいつに押し付けられたんだよ」
「確かにちゃんと世話してもらえる人物といったら貴方とポーラくらい…アルドは?」
「同じくシーアについていってるし、あっちはもう一匹いるだろう」(険悪)
「…ああ」(苦笑)
「おまえよー、もうちょっとかまってやれよ。心配してるぜこいつ」
「お前に言われたくないっ!」
(あんまりにも機嫌が悪くて相手を突っ撥ねるのも忘れてたりする罠。
お陰で面白くてつい突っかかる海賊二人組み。(ハーヴェイとシグルド)
でもこの二人ならそれなりに付き合いがありそう。ていうかなきゃ困る…(いろいろ)
(なんて書いてた板)


「…何?」
「ん? いやぁー」
「いやあーって。何」
「別になんでもー」(さわさわ)
(…なんでもないだろうから聞いてるんだけど)
(セクハラ?(違))
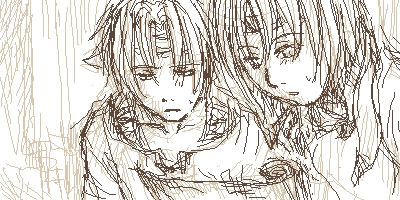
体の奥から底冷えするようだった。ぞわと身の毛が弥立ち、言葉を失ってただ手にした用紙を見つめる。
細かな設計、付け足された説明、紙の端に走るメモ。幾度も修正された跡。
そして完成された形、造り上げる術、戦の間でも、共に戦う仲間にも、自分にも軍師にも海賊の頭にも、一国の王にすら知らされなかったもの。
「これが…」
「紋章砲の設計図だ」
不様に手が震えてしまいそうだった。
「…これを、僕が? ウォーロック」
「そうだ」
顔を上げて問えば、やつれた表情を見せる老人が頷く。
「儂がお前に渡したい。その上でお前がそれをどうするかは好きにしろ、焼き捨てるなり王にでも渡すなりな」
「…何故僕に?」
「儂が渡せると思えた人間はお前しか居ないからだ」
澱みなく告げられた言葉を、シーアは黙って受け止めるしかなかった。言葉なく戸惑う様子を表に出す彼に、ウォーロックはふんと笑う。
「お前は相変わらずだな。己の価値をわかっておらん」
「価値って…僕がこんな大事なものを持っていても、どうしようもできないのに」
「お前の好きにしろと言っているだろう。」
「…」
「お前ほどの地位の人間たちはまず自分の国を護ることを考える。だからこれを破却することは絶対に出来ん。他人に渡すこともな。そんな選択肢の狭い奴に渡すことなど出切る訳がない。
その分お前は違う、お前ならもっと広い視点を持つことが出来る。無き物にすることも誰かに渡すことも出来る。無論己が持ち続けることも」
「…ウォーロック」
しわがれた顔が歪む、眼鏡を弄りながら、彼は静かに言葉を続けた。
「捨て払っても恨みはせん。ただあまりにも、誕生が早かっただけだからな。人はいつか、この紋章砲と同等の力を、己の手で生み出すだろう。」
「…」
「その為に残しておいても構わん。だが同じ対抗する力が出るだろうから、無意味になるかもしれんがな。
…封印されるに越したことはない」
最後の言葉は、つかれきった色を濃く乗せて呟かれた。一瞬鎮痛の面持ちになるも、すぐに引き締めてひとつ間をおいてから、シーアは頷いた。
「判った。これは僕が預かる」
「…すまんな。
やれやれ、船の連中はただの人間にとんでもない重荷を背負わせるものだと思っていたのに、わし自身が最期に重荷を背負わせるとはな」
肩の力を抜いて呆れ混じりに吐いたウォーロックに、シーアもまた暫し顔を緩ませて応える。
「平気だ、僕を信頼してくれていると判っているから。」
「人の良さも相変わらずだ」
重い動作で立ち上がる、ゆるりと部屋を出ようとする彼を、シーアは呼び止めた。無表情に振り返るウォーロックに寄って、言葉なくシーアはただ、手袋を脱いだ左手を差し出す。目をしばたかせて暫し訝しげに様子を見ていた彼は、ただじっと相手の応答を待つ彼にため息をついて手を上げる。掌に掌を合わせると、シーアの指が彼の手を包む。
じわりと伝わる人の温度。そして年齢を感じる肌の感触。
「…左手でごめん」
「なにが言いたい」
うん、とシーアは笑う。
「…これから、王宮へ?」
「そうだな。裁判の有無を聞かねばならんからな」
「そう…」
沈黙が落ちて、わずかに時が流れてからシーアはつと息を吐いた。
「紋章砲はこれから、島中で議論が始まる。規制のみで終るか、封印か。まだ判らないけれど。人々も注目するだろうと思う、反対する人も賛成する人も、大勢現れる。
…きっとその中には、ウォーロックを非難する人も、出てくると思う」
「だろうな」
半ば罪滅ぼしで島を護るためにシーアたちに手を貸した。けれどそれで何もかもが帳消しになるわけではない。寧ろ彼の罪は、一生かけても償えぬものかもしれないと思うほどに、紋章砲による被害は膨大なものだった。
彼もそれは十分に承知しているのだ。
「だけど」
柔らかく笑いながら繋がった手に力を込める。兵器を作り出した掌を包み込むのは。
「僕は、世界中の誰もが貴方を許さないと言ったとしても、僕は、僕だけは、
貴方を許したいと思う」
皺が寄ったその面持ちが、驚きに変わった。笑いながら再度、シーアは言葉を彼に向ける。
「僕は貴方を許すよ」
じんわりと左の甲が疼く音が、広がった様に感じる。それは水の様に緩やかに流れていき、そして音もなく静まっていった。
ゆるりと繋げた掌を開いて、どちらともなく手を離す。
顔をあわせて視線を交わし、最期に一瞬、そのやつれた面持ちに泣きそうな笑みを浮べた。だがすぐにその表情は消え、ではな、と背を向けて彼は部屋を出て行った。
「…シーア」
老人の背を見送った姿のまま立ち尽くす彼を気遣うように声をかければ、弱々しい相槌が返ってくる。手に持った大切な預かり物を抱えながら、ポーラは空いている手を、そうとシーアの肩に置いた。
「戦争のために」
ぽつりと、シーアが言葉を吐き出す。
「戦争に使われるために生み出した訳じゃないと、いつだったか聞いたことがある。
ただ研究をしたかったんだと、紋章を知るためにつくったのだと。
…それを利用したのが戦争する人間たちだっただけだ」
「…王はきっと判ってくれます。」
こくりと彼は頷く。
「頭の痛い話になるけれど、リノさんなら少しでも良いようにしてくれると僕も思う。
でも何故だろう。何故彼は、今僕にこれを渡しに来たのだろうか」
俯いた面持ちのまま視線をゆると動かして紙を見やる、ウォーロックが掌に納めていた時の事を思い出して、じりと胸の奥が騒いだ気がした。
近い未来、彼は思う。その胸の不安は気のせいではなかったのだと。彼は恐らく、己の死期を感づいていたのではないかと。
(結局は人間の手がそれを兵器にもそうじゃないものにも変えてしまうんだろうと)

聞きなれた足音と懐かしい匂いが同時にやってきて、俯かせていた顔を上げるとすいと目の前に白い棒の形をしたものが差し出される。
目をしばたかせ穴が空くほど見つめた後、口の中に苦味が広がりつつも笑った。
「吸い過ぎんなよ、身体に支障が出るぜ」
「まず言いたい事はそれか」
呆れたレイの声に、テッドは笑ってそうだと応えた。
「にしても、俺が吸えるって何時から知ってた?」
「まだ君が僕の家に居たときから」
ぴた、と煙草に手を伸ばした彼の動きが止まる。ちらと視線を上に、煙草をくわえたままにやりと笑う親友に行き着く。
「ときたま匂いがね。完全に消したと思ってた?」
「思ったんだけどなあ…」
先ほどとは違い本当に苦々しそうに呟くテッドに再度笑う。
「あの頃が一番良く隠れて吸ってなかった?」
「…それが敗因だったか」
「ぱっとやめたみたいだけど」
ああ、と相槌を打ちながら視線を隣に移す、肩に寄りかかりながら目を閉じている存在がひとつ。ぼさぼさと乱れた木蘭の髪も泥だらけの服もそのままに、双剣を抱えて眠りに付いていた。
「やっぱり、シーア?」
「激怒されたよ。内臓は魔法治癒がかかりにくいからどんなに体が丈夫でも内臓の故障でころっといっちまう奴も多いんだから、やるなら自制利かせろってな」
げんなりといった口調のテッドに苦笑が漏れる。さぞかしシーア激怒がきつかったのだろうと思う。
「まあ実際、これが原因で体力は落ちてたから反論のしどころがなかったんだけど…、所で火は?」
ん、と煙草を近づけて来るのに、渡された煙草をくわえて火を分けてもらう。ふと息を吐けばふわと浮かび上がる白い煙。
「…物事を考えすぎてどうしようもなくなった時」
ぽつと、城壁の向こう、戦場の痕そのままの平原を見つめながらレイが呟く。
「そんな時に頼っちゃうんだよね」
「…わからないでもないけどな」
彼とは反対に城壁の中に視線を向ける。思い思いに辺りに散らばって床に転がる兵、自分のように無言で武器の手入れを行なうものもいれば張り詰めた面持ちで辺りを警戒する見張りの者も居た。松明が柔らかに辺りを照らしていても、その光景は殺伐としている。
「…お前はどう思う?」
淡々とした言葉にレイは一度テッドに視線を向けてから、再度城壁の向こうへと移す。
「やはりランが先頭に立っていた時ほどではないな。だけどあの時の結束はまだ続いている、乗り切れるだろうとは、思うよ」
「…そうか」
歯切れの悪い返事、眼を瞬かせてレイは彼を見る。
「何か心配事でも」
「いや、そうじゃないんだが」
「…見方、少し甘い?」
そうでもないと首を横に振る。だがすっきりしない彼の対応に、レイは口を閉ざした。時折はぐらかされることもあったが、急かさず待っていれば言葉は出てくるのでそれを待った。
「行方はわからないんだろ? あの紋章」
暫し逡巡の色を見せて、ようよう出てきた言葉にレイは是と答える。
「俺も詳しい事を知っているわけじゃないが、噂も考慮して野放し状態と思ったほうがいいんだろうな」
「多分。…テッドは、この戦が獣の紋章を引き寄せるための手段だと考えているのか」
「真の紋章って言うのは戦を引き寄せるものが多い、だからそれも含まれているかもしれないと思ったんだ。」
「…だとしたらとんでもないことになるな。」
過去の戦争の話はまだ記憶の中では新しい、実際目の前で見て対峙した知り合いの話を思い出し、レイは眉をひそめた。
「俺の懸念しすぎかもしれないけどな」
「けれど考慮にいれておいたほうがいいだろうな。
…ああ、もしかしたら」
「どうした?」
何かを思い出したように呟いたのに問い掛ければ、レイは苦笑を漏らしてかえしてくる。
「ラン、今皆に顔を合わせに行っている。あれだけ陰でこそこそしていたのに突然どうしたんだと思っていたから…もしかしたらランも同じ所に気付いたのかもしれない」
「道理で姿見かけないと思ったら…大丈夫なのか?」
元々自分たちは戦に介入すべきではないと判っているのに陰で手を貸しているのは、その知り合いのために他ならない。数年前デュナンで起こった戦争の中心に存在した少年、一度は身をくらましたが戦の話を聞きつけ駆けつけていた時に再開した。話を聞いてしまえば、そのまま知らぬ振りをすることも出来ず、彼と共に陰で手助けをしている。
「騒ぎ出す者もいるだろうけど、テレーズもシュウもわかってくれる人だから。」
「なら、いいけどな」
ふうと息を吐く、煙がゆれて上っていくのを見ながら言葉ひとつ。
「来るか」
「多分ね」
ふと、双方からため息が漏れた。
(隠し部屋設定。捏造失礼でハイイースト…らしきもの?)
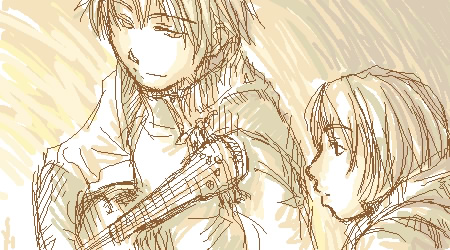
(…あ)
見たことのある輪郭が目について、つい手が伸びてしまった。覆うように被っていた布を剥ぐと、あらわれたのはやはり見慣れた形の楽器。
(懐かしいな)
随分昔の事を覚えている自分に少々驚きながら、指先で丁寧に手入れが施されている楽器に触れていた。
「弾けるのかい?」
物思いに耽っていた所為で見られていたと気付かず、後ろから声を掛けられてひくりと身体が跳ねた。慌てて持ち上げようとしたのをそろりと地に下ろす。
「すいません、つい」
「いや、いいよ。懐かしそうに見てたから弾いたことがあったのかと思ったんだが」
「はい、一応昔、少しだけ…」
「そうならちょっと弾いてみる?」
穏やかそうな女性に餌を釣られ、否定する事を忘れていいんですかとついくいついてしまった。しまったと思いつつちらと彼女の夫である男性を見ると、柔和の面持で彼は頷きひとつ、テッドに見せた。隠せず、口元が緩む。
「じゃあ、すいません、少しだけ」
袋ごと抱えて、彼らが集まる焚き火の元へ行く。椅子代わりの丸太に腰を下ろして、袋から楽器を取り出した。艶のあるからだが火の光に照らされて恭しい存在感を醸し出す、その姿。
「何時それの事を?」
じっと見つめていたときに問われて、苦笑しながら答える。
「昔、吟遊詩人の人と旅を一緒にしていた事があって。その時に教えてもらったんです。随分昔の話なんで、指が覚えてるかどうか」
「案外そういうものは、身体は驚くほど覚えてるものだよ」
かもしれないと思いながら、記憶を思い出すこともしないまま音を合わせていく。弦をはじくと溢れる音がとても懐かしくて、端から見れば怪しいほどに笑っているのではないだろうかと思う。
「テッドは何が弾ける? 昔の歌を何か知ってる?」
母と共に座っていた少女の問いに、暫し逡巡してからにやりと笑い。
「こういうものなら?」
ぴんと指が爽快に弦を弾き始めた。軽快な音色が流れ始め、音に合わせて歌を紡ぐ。
「"ヘイ、ディドル、ディドル!
ネコにバイオリン
牝牛が月を、飛び越えた♪
犬はそれみて大笑い
そして皿はスプーンと一緒に、おさらばさ"♪」
くすくすと笑いが溢れた。にっこりと笑い返しながら歌が終ると、少女が寄って来た。
「なにそれっ。 聞いたことないよ」
「随分と昔の童話だね、それも同じ人に?」
「そいつが古い歌が大好きだったもんで、俺もこんなのしか」
「後は、何かないの?」
せがまれて何曲か差し障りのない曲を弾いていく。穏やかな雰囲気が流れ、何度めかの曲を弾き終えた後。ふと女性が隣に視線を移して微笑んだ。
「あら、貴方も興味を持ったかしら」
背後に視線をやれば、先程まで離れた場所で眠っていた彼が屈み込みながら楽器をまじまじと見ていた。その様子に思わず笑みが零れながら、テッドは言葉を紡ぐ。
「…お前、見たことないから珍しいんだろ」
頷きひとつ。
「ていうか元々興味もなかったか」
暫し沈黙、のち僅かに首をかしげて。
「…そうでもないのか? …ああ、音楽ってものに触る機会がなかったのか」
是と頷く。
「…よく会話出来るね」
ぽつりと呟く少女ににっこりとテッドは笑う。
「見てると、案外こいつは顔に出るタイプだからな」
「そうかなー。何しても顔変わらないんだけど」
少女が手を伸ばして彼の頬を遠慮なく触るも、確かに彼の面持ちに変化はない。だがテッドは彼が少々むず痒そうにしていると読み取れて、それでも動かない彼に呆れ笑いが浮かぶ。
「こら、なにをしてるのっ」
母親に叱られてひゃっと手を離し肩を竦める少女に苦笑しながら隣をみやれば、彼は無言で首を横に振る。
「気にしないでください、こいつも気にしてないってさ」
「でも…」
「…口数が少ないだけだから。こいつ、人といるのは嫌いじゃないし。
だからまた遊んでやって欲しい」
最後の言葉を少女に向ければ、少女はにこりと笑い返し、そして隣にも笑いかけた。
首をかしげて無表情のまま受け取るも、テッドには僅かに口元が緩んだように見えた。そしてそれは気のせいではなかった。
「あ、ほんとだ」
あなたも笑うんだねえと少女が笑うのに目を瞬かせて、視線を彷徨わせながら僅かに頬を染める。その様にまた少女が笑うので、テッドの背に隠れるように俯いた。
ああ、ちょっと可哀想かも。
そう思いながら口元から笑みが消えない。
「照れるなって」
ちら、と彼が自分を仰ぎ見るも。にこにこと笑ったテッドの様子にかすかに顔をしかめた。そんな事もお構いなしに。
「な? シーア」
(封印するか迷ったんですが…もういいので晒しものにします。シーア無口設定話…だけど多分もう書かないかなあ)