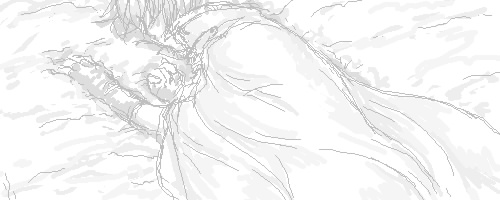
ひやりとした冷たさ、羽毛の様に柔らかい手触り、ほんの少し触れただけで溶ける儚さ。
(気持が良い)
そうと目を閉じる。音をすべて包み込むそれに横たわりながら、感じる。
そして、思う。
(何も感じなくなればいいのに)
「……なにしてるんだよ」
呆れた声が振ってくるのにゆわりと笑う。
「雪に埋もれてる」
「風邪引きたいのかお前は」
「引いたら看病してくれるかな」
「……そのまま動かなかったらしないぞ」
睨み付けられて、勘弁してと笑って交わす。
そわりそわり。
白い結晶が舞い降りて、不意にその方を見上げる。空から小さな雪が降り始めた。
静かな光景、風もない今はただ、雪が舞い降りていくだけ。後は自分と彼の、微かに息をする音だけが響いている。
耳鳴りが遠く、遠く。ひいんと鳴っている。
「…」
外套の上に薄らと雪が積もって来た頃、ようよう片手を空に上げる。間を置かず手を取られ、引き起こされる。
雪を払い落とし、息をつくと微かに身体が震える。外套を纏っていたとはいえ、やはり寒さが身体に入り込んでいた。
「あー、ったく。すっかり冷えてるんじゃないか」
「んー…」
雪に触れて赤みがかっていた頬に手が伸びて、包み込まれる。じわりと伝わって来る暖かさが心地よくて、わずかに目を細めた。
「霜焼けになるかな…」
「…そこまで我慢するなよ…」
呆れ半分憤り半分、その声にへらと笑って、ゆるりと寄った。反応を返して来ない相手をそのままに、その肩に頭を乗せる。彼の纏う外套も随分と冷たくて、自分と同じく長い間外に居たのだと知らせて来る。
ふと感じていた寒さが、暖かいものに変わる。気付けば彼の外套に自分の外套ごと身体を包められていた。
「…寒くないか?」
「寒い」
「……」
「このままだと俺も風邪引く。それに腹も減ったんだ。だから…まずは宿の女将さんにでも、暖かいものを貰いに行くか」
彼は、笑う。それに何とか、笑い返して是と答える。
ゆっくりと歩き出す彼に連れられて、白い空間を後にする。音のない柔らかな世界、耳に残る静寂、酷く心が穏やかになる所。
それに入り込む、人。
(判っている)
ここにいるべきは、自分ではない。彼は優しいから、生きる術を見失っている自分を放っておけないだけなのだ。自分でもどうにかして生きようとしているのだが上手く進めなくて、そんな自分に自己嫌悪を感じて更に道を見失っていく。いまだに手を引かれて覚束ない足取りで歩みを進めている、情けない状況だった。
(動かないと)
焦りばかりが募っていく。その度に、身体が動かなくなっていく。心ばかりが暴走して、身体がついていかない。
いっその事心が何も感じなくなればいいと思う。雪の冷たさも、人の暖かさも感じられなくなるが、痛みも辛さも判らなくなる。判らなければきっと自分は歩いていける。昔は歩けたのだから。
(でも、それは逃げだろうか)
全てを無視することは、自分に起こっている事も自分の目の前で起こった事も見ない振りする事だ。平穏は保たれるかもしれない、けれど、生きていく上で、それは良い選択なのか。と、
口元に、苦味が広がる。
(…そういう事だったのかな)
目の前の後ろ姿を見上げる。黙々と歩く背と繋がれる手。…今更彼の心情を悟ったかもしれない。
ごめんと心で呟いて、繋がれている手を握りしめる。
今はこの手に縋るしかない自分を許して欲しいと、必ずこの手を、離すからと。細い糸を手繰る様な気持で、思う。
やんわりと手が、握り返された。

某ヒロインの設定に燃えてしまった一枚…(…)

「…ポーラ」
死んだ魚を何故か連想してしまう、そんな声で彼は言葉を紡ぐ。
「穴って、ないんだろうか」
「…穴、ですか」
「うん、穴。ほら、何処かの言葉であったじゃないか」
「…つまりは穴に隠れてしまいたいという事ですか」
「そう」
こっくりと頷く。哀愁漂う背をポーラに見せながら、彼は虚ろ気に呟く。
「…僕は莫迦だ」
「シーア…」
「……〜〜〜」
ぐしゃぐしゃに髪をかきまわしながら俯いて、唸り出す。……感情の捌け口に困っている様だ。彼がこんな思いをするのも滅多にない事だから仕方ないのかもしれない。どう手を差し伸べればいいのか判らずにいるポーラにも、彼のこんな姿は珍しかった。
「莫迦だ、ほんとに莫迦だ…
……なんであんな事を言ったんだろう」
困った様に首を捻って、そろりと近付く。丸まっている背にそうと手を置いて、ポーラはシーアに声をかける。
「…友達に、なりたかったのでしょう? 彼と」
「………」
きう、と両の手が握りしめられる。断られた言葉でも思い出したのだろうか。本当に彼にしては珍しく、いまにも泣き出しそうな面持ちだった。
「……きっと迷惑だったよね。
突然友達にならないかなんて、今さっき顔を合わせて、ほんのちょっと一緒に話して、闘っただけなのに…」
「そこまで、シーアに言わせる何かがあったんじゃないですか?」
「…」
困った様に視線を上げて、すぐに下げる。戸惑いながら、それでもぽつりと。
「……多分紋章の所為だ」
「紋章ですか」
「多分。──多分それで、何故だか前に会った事のあるような、そんな親近感が、あった」
そうか、とポーラは思う。シーアは以前の身の置いていた所もあって、安易に自分の中に人は入り込ませない。ある程度までは親しく出来るが彼の本音や表情を見せるようになるのは随分と時間がかかる、騎士団の仲間のタルやケネス、ジュエルにも年相応の表情を見せる迄、彼なりの自分を曝け出す迄に一年を要した程。それが彼の処世術で、ほぼ無意識の行動なのだが。
紋章の事はポーラは判らなかったが、もしかしたら共鳴か何かを起こす事もあるのかもしれないと思った。そして普段は初対面では感じられない親近感を持ち、彼はきっと本音で言葉を言った。そして払われた。
………言ってしまえば傷心中なのだ。
つい口元に笑みが浮かぶ。不謹慎だが、滅多にない彼の姿を微笑ましく見やる。横に座り、覗き込む様に彼を見た。
「シーアは、どうしたいですか」
「…」
「確かに唐突だったかもしれません。彼も驚いたかも知れません。
……でもそれだけでしょうか。彼は、他になにかを抱えているように見えてなりませんが、シーアはどうですか」
「…」
応えは返って来ないが、透き通った蒼の瞳が彷徨って居た。視線を横に投げる仕種は、彼が物事を考えている時に行う癖だ。
「あの様子ですときっと彼は、あのまま誰とも関わらずにいようとするんじゃないでしょうか。
シーアはそれを、どう思いますか。
……シーアは、どうしたいと思いますか?」
「…」
視線を上げて、すぐに下ろし、暫し沈黙があった後、再度視線を上げて、
「…話を、してみたい」
その言葉に、ポーラは微笑んだ。
(テッドに対する行動のはじまり。うちのポーラさんは後押しタイプ)

全力疾走した後の様な呼吸が響いている。闇の中に僅かに差し込む月の光だけが灯りとなって、互いの姿を現している。一人は静かに、寝台で仰向けになり、一人は肩を揺らし息を繰り返しながら、下の者に刃を突き付けている。
荒い息だけが響いている、その中に、ぽつりと。
「…シーア」
刃を突き付けている少年が、呟く。ゆるゆると状態を起こすと同時に、短剣を彼の首筋から離して行く。腕を両肩から垂れ下げて、深く息を吐く。
「すまない…」
(持つ者達の元ネタです)

細く細く 糸のような
けれど途切れる事のない印

1前設定のうちのテッドとシーアさん
こんなことを節操なく出来るテッドさんだといい